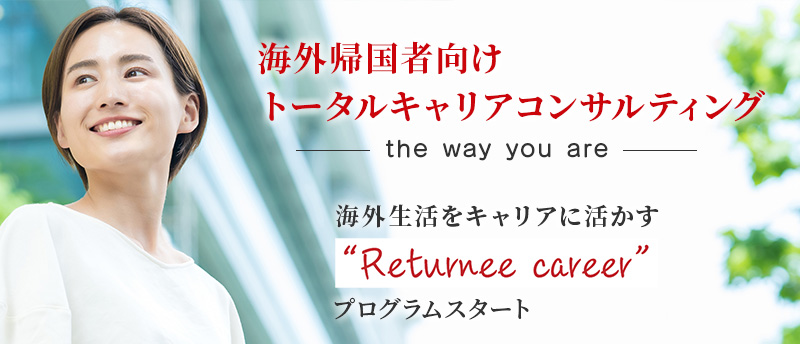パソナインディア新入社員が語る、インド就職のリアル
先月入社したばかりのパソナインディア社員の体験談です。学生時代に旅行したインドに、「就職」というかたちで戻ることを選択した理由、インドでの生活を始めて感じたことについて教えてもらいました!
自己紹介
2025年5月にパソナインディアに入社いたしました。前職では地方自治体の職員として、選挙や統計調査に関わる業務に従事していました。インドに来て約三週間、日本での生活、前職とは全く異なる環境で、刺激的な毎日を過ごしています!
なぜインド就職?
国際日本学を専攻していた学生時代、異文化交流や海外でのキャリアに対して興味はありました。ただ一方で、言葉や食事、文化の違いへの不安もあり、海外で働くことが自分にとって現実的ではないと感じていた部分もありました。日本の生活や地元がとても好きだったこともあり、将来海外に出て「働く」「住む」というイメージはあまり持てていなかったのかもしれません。
しかし、学生時代に旅行で訪れたインドでの経験は、ずっと心に残っていました。街のエネルギーや人々の熱気、多様な人々や価値観が混ざり合う空間の中で、強烈な衝撃を受けたことを今でも覚えています。あの時感じた感覚が、心のどこかで自分のリミッターを外してくれたような気がします。
社会人として経験を積む中で、「もっと広い世界で自分の可能性を引き出したい」「インドをもっと知りたい」という思いが次第に強くなっていきました。インドはとてつもない成長力と多様性を持ち、人口や経済もまだまだ伸びていて、あらゆるところにチャンスが広がっているように感じます。日系企業も多く進出している中で、私もその一翼を担い、人と組織の両面からサポートできる人材になりたいと考えるようになり、最終的にインドでの就職を決意しました。
インド人の働き方
インドには「ジュガード/ジュガール」という言葉があります。これは「即席の課題解決法」「限られた資源や条件の中でもなんとか問題を解決する」という意味で、困難な状況でも創意工夫で乗り越えていく精神を表しています。日本人の特徴として、緻密な計画を練り、可能な限り失敗のリスクを軽減することに重きを置いていると感じますが、ジュガードの教えのもとでは、失敗や困難に直面した時に、どのように柔軟な解決策を生み出すかが重要です。また、インド人は時間や期限を守らないといったネガティブな印象を持つ方も多いのではないでしょうか。これもまた、予定通りに厳密に進めるよりも、状況に応じて柔軟に対応することを重視するからこその傾向と言えるかもしれません。どちらか一方が優れているとは断言できません。こうした日本と異なる価値観に囲まれた環境で、自分の視野を広げたり、可能性を引き出したりすることができるのも海外就職の醍醐味ではないでしょうか。
インドでは、個人の成果や実力がしっかり評価される一方で、何よりも人とのつながりや信頼関係が重視されていることが印象的です。ビジネスの現場でも、良好な人間関係が仕事の成果に大きく影響すると考えられており、チーム内での助け合いや協力体制が自然に根づいていると感じます。その根底には、インド社会における「家族」の存在の大きさがあるとも言われています。インドでは、家族とのつながりや家族愛が非常に深く、家族は生活の中心であり、価値観や行動の基盤でもあります。仕事中にも家族と電話でやり取りする姿をよく目にしたり、職場に限らずインドの方々は家族の写真を嬉しそうに見せてくれたりします。

―インドに来て初めての食事は日本食。クオリティも高く、しばらくは日本食ロスに耐えられそう。
インドの暮らし
ここではインドの生活について少しお話ししたいと思います。インドの暮らしと聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?カレー?牛?ヨガ?暑さ?どれも間違いではありません。しかし実際に暮らしてみると、「インドらしさ」がだんだんと癖になってくる瞬間があります。たとえば、インドの道路はクラクションの音が鳴りやまないことで有名です。日本では非常時にしか使わないもので、むやみに鳴らせば不快に思われたり、煽りや挑発と受け取られることもしばしばありますよね。私が初めて旅行でニューデリーを訪れたときも、耳を塞ぎたくなるほどのクラクションの嵐に驚かされました。まるで街全体がイラついているかのような威圧感があって(のように感じて)、横断しようとしたときにはその音に圧倒されて、足がすくんでしまうくらいでした。それが今となっては、クラクションの音すら安心感を与えてくるようになりました。確かに、ネットで「クラクションが一種のコミュニケーション手段になっている」といった記事を読んだことはありましたが、やはり自分の肌でダイレクトにそれを実感したからこそ、ものの見え方が変わるという大きな経験でした。ほんの小さなことではありますが、こうして少しずつ自分の中の「当たり前」がほぐれていくのを感じる毎日です。インドでの生活は、違いに驚き、戸惑いながらも、それを受け入れ、馴染んでいく過程の連続でとても楽しいです。
休みの日は家にこもるのが苦手なので、住んでいるデリーのあちこちを探索しています。ローカルマーケットをのぞいてみたり、歴史を感じる世界遺産や博物館を訪ねたり、自然を求めて大きな公園を歩いたり。時には、大きなショッピングモールやグルガオンのような急成長都市にも足を運び、インドの急速な発展ぶりに感心させられています。車を少し走らせれば、たいていの場所に行けてしまうのがデリーのいいところで、「ここに住んでよかったな」としみじみ感じます。ついつい日本と比べて安いタクシーに頼ってしまいがちですが、たまにはデリーのメトロやバスに乗って移動する“ツウ”な楽しみ方も悪くないな、なんて思っています。

―夕日に染まるフマユーン廟。その建築スタイルはタージ・マハルにも影響を与えたとか。
最後に
「インドに行く!」
そう家族や友人に告げたときの反応は、今でもよく覚えています。多くは驚きと不安に満ちたものでした。
「なんでインド?」「危なくないの?」「価値観変わるって本当?」
インドに対する漠然とした先入観やイメージが戸惑いの背景にあることがよく伝わってきました。しかし、私が海外転職を決めた理由や、インドという国に対する思いを丁寧に話すうちに、少しずつ反応は変わっていきました。
「インド怖かったけど、行ってみようかな」「やっぱり人生で一回は行かなきゃ」「せっかく友達が住んでいるなら、いい機会かも」「インド、なんか面白そう!」
こうして身近な人たちがインドに対して興味や好意的な感情を持ってくれたことは、私にとって本当にうれしい出来事でした。
国際的に見ても、世界一の人口を有する国であるインドは常にさまざまな視線の中に置かれている国だと感じます。近年では豊富なIT人材や大企業のCEOにインド人が起用されるなど、インド人の存在感が非常に大きく、高く評価されている一方で、受け入れ側とのコミュニケーションの違いや高い離職率、現地人材との雇用競争などから、一部ではインドという国に対する捉え方が必ずしもポジティブではないことがあります。日本でも大きく報道されたパキスタンや中国との関係は、政治的、歴史的な緊張を背景に、国際関係の文脈でも注目されることが多く、これもまたインドという国のイメージ形成に影響しています。
日本ではここ数年、特にビジネスの分野でインドへの関心が高まってきたように思いますが、一方で私の家族や友人同様、一般の感覚としては「治安はどうなの」「食事が合うか不安」「インド人のことはよく知らないけど苦手かも」「衛生面が心配」など、まだまだ慎重な声が多いのも事実ではないでしょうか。最近では、SNSやYouTubeの影響もあり、「インド旅行」や「カルチャーショック」といったテーマで発信される動画が目立つようになりました。中でも「不衛生」「詐欺にあった」といった、ショッキングでネガティブな内容が強調されているものも多く、そうした動画は視聴数を集めやすいこともあって、ある種のエンターテインメントとして消費されているように感じます。もちろん、それらの動画の内容すべてが事実無根というわけではありませんし、インドには課題や不便さがあるのも事実です。ただ、そうした一面的な印象ばかりが先行し、インドに対して偏ったイメージを持つ人が増えてしまうとしたら少し寂しい気もします。私が渡航前に思い描いていたインド、そして実際に暮らし始めてみて感じるインドは、それよりもずっと複雑で奥深く、一言では言い表せない魅力があると感じます。自分の目で見て、肌で感じるからこそ見えてくる景色があると思います。ここまで読んでくださった皆様、インドで待ってます!インドに限らずどこであっても、新しい環境に飛び込む経験は、自分を見つめ直す良いきっかけになるはずです。

まずはご登録からパソナインディアの転職サービスに登録する海外転職を成功させる1番の秘訣は、エージェントの質と現地での実績です。
2006年インドで初の日系人材紹介会社として誕生以来、数多くの転職を成功させてきたパソナインディアに安心しておまかせください。